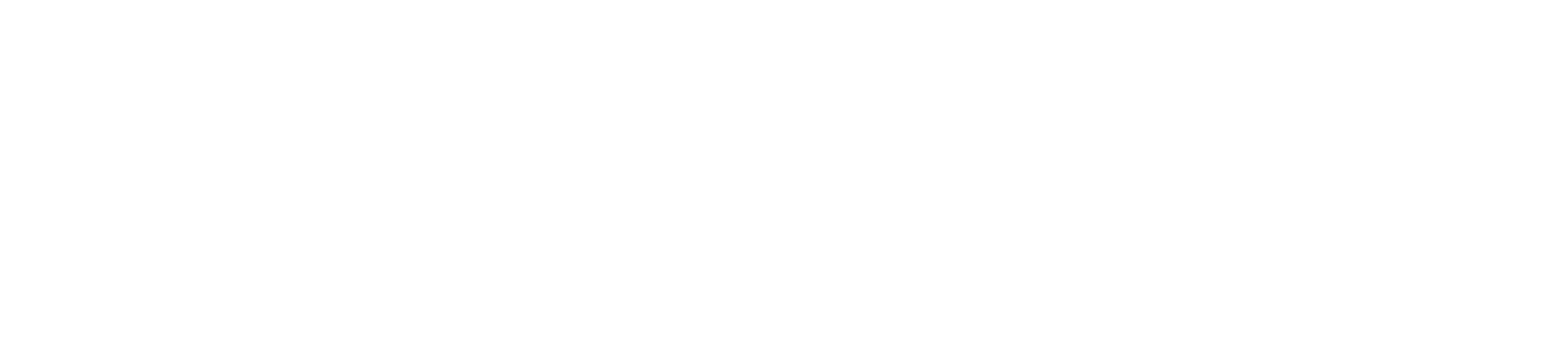私たちZenportは、「グローバルサプライチェーンに、共通言語を。」をミッションに掲げ、サプライチェーンの分断という課題に取り組んでいます。
今回は、弊社のダイバーシティなメンバーや働き方を紹介するシリーズ第1弾です。派遣社員から正社員に転向し、Zenportの勢力を伸ばすうえで欠かせない、入社4年目のSumikoさんにインタビューします。
Q.まずはSumikoさんの自己紹介とバックグラウンドを教えてください。
大学、大学院と建築学部を専攻し、卒業後はゼネコンに入社しました。2つの社内ベンチャーの経験と産休、育休を経て退職しました。育児が落ち着いた後、派遣会社に登録し、HR企業のIT部門や中堅SIerにてキャリアを渡り歩いてきました。その後、コロナ禍に派遣会社からZenportを紹介されて、派遣社員として入社することとなりました。
Q.初めは派遣社員からのスタートだったのですね。正社員に転向されたきっかけや理由は何ですか?
正直、入社した当初は正社員になることを考えていませんでした。派遣社員の個人抵触日となる3年が経つ頃、有難いことにCEOのOtaから「引き続き我々と一緒に働いて欲しい」というオファーをいただきました。当時、これまで派遣社員と正社員という垣根を感じることなくやってきたため、オファーを引き受けることにしました。正社員として引き続きZenportにコミットしようと考えた理由は、お客様ファースト思考、メンバーのサポート、働き方の柔軟性があるからです。
入社3ヶ月が経った頃、時間外にOtaから急ぎ対応すべき業務の連絡がありました。正直、その当時は「派遣社員に求めてくるか」と疑問に感じたことも事実です。しかし、スタートアップということもあり、誰かが私の業務を代わりに担ってくれるわけではありませんでした。悶々とするなかでも感じたのは、Otaの純粋なお客様を思いやる姿勢でした。
また少人数のチームだからこそ、一人ひとりが重要である一方、自分のやり方で業務を推進できる自由さは私に合っていると感じています。弊社の特徴の一つであるダイバーシティなメンバーは、国籍や居住地も異なりますが、いざとなったら必ずサポートしてくれるのも心強いです。
加えて、私にはまだ小学生の子供もいますし、Zenportの業務とは別に個人でやっている活動があるため、働き方に柔軟な点はありがたいですね。メンバーは正社員だけでなく、業務委託や派遣社員など、雇用形態も様々ですが、「一人のビジネスパーソン」として公平かつ厳密に評価してくれて、どのような立場でも意見を聞き、反映してくれる点も働きやすさに繋がっています。
Q.雇用形態の関係なく公平に評価されるのは、ビジネスパーソンとして喜ばしいことですね。 働くうえでの苦労や大変なことがあれば教えてください。
先ほどお話ししたように、スタートアップで各々の領域があるため、現時点で私の作業をまるっと他のメンバーへ任せることは難しいです。あるとき、重要な案件が進んでいるタイミングで体調を崩してしまったのですが、自分の担当部分は対応していました。それは会社側から強いられたわけではなく、Zenportで働くうえで自身の使命感のようなものが身についたからこそ、遂行したいと思い対応しました。
また、社内は英語を公用語としています。私自身、元々英語には興味を持っていたものの、いざミーティングやクライアントとの打ち合わせで使うとなると、聞き取ることがやっとの状態です。言語に関しては、日々努力していますがメンバーのサポートもあり、徐々に伸びていると実感しています。英語にアレルギーがなければ、働きながら実践的な英語を身に付けられるのも弊社の魅力だと思います。
Q.成長する機会の多い現場ですね。最後にこれからジョインしてくるメンバーへメッセージをお願いします。
弊社に限らず、スタートアップ企業で働くには、ある程度の自走力が必要です。少数精鋭のため、個の対応範囲も幅広く、時として自身の能力が企業に大きな影響を与えます。
弊社は雇用形態や国籍、能力に関わらず、メンバーの意見に耳を傾けて、お客様のためにチームで課題解決に励んでいます。否定的な考えやご自身のやり方に強いこだわりを持つ方はアンマッチだと感じます。反対に、素直さと向上心があれば、吸収できることは山程ある環境です。グローバル、サプライチェーン、IT、英語への興味など、自身の成長と企業の成長に対して意欲的な方はぜひ私たちと一緒にはたらきましょう!
Sumikoさんありがとうございました。
今後のさらなる活躍が楽しみです!

▲第3回スマート物流EXPOにて撮影(2024/1/24~26)
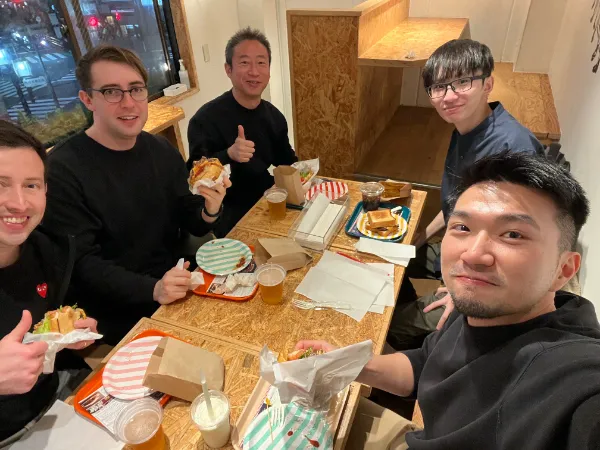
私たちZenportは、「データ・人・経済をつなぎ、持続可能で協力的な世界を。」をパーパスに掲げ、データ連携を切り口に、グローバルサプライチェーンを通じ、分断しない世界をつくっていきたい、世界の人々が協業して持続可能な姿で豊かになっていく世界を創りたいと考えています。
今回は、弊社のダイバーシティなメンバーや働き方を紹介するシリーズ第2弾です。現在のZenportのサービスを立ち上げたCEOのFumiさんにインタビューします。
Q.まずはFumiさんの自己紹介とバックグラウンドを教えてください。
大学卒業後、新卒で三菱商事にて8年半、その後MBA取得、ボストンコンサルティンググループ(BCG)、ミスミにてキャリアを歩んできました。
三菱商事で製造業の海外営業、BCGにて新しい領域での事業分析の基礎、ミスミにて製造業及び流通業の知識や考え方、お客様の声をどのように事業に活用するかを学びました。
ちょっと唐突ですが、まず、自分が原体験的なものとして思うのは、幼少時に思った、ものごとの意味は文脈によって変わる、という理解です。
さして特別な体験があったわけではないのですが、日常生活、例えば、地元の小学校でちょっと成績が良くても塾に行くと落ちこぼれる(これは一応挽回しましたが)、あるいは転校したり海外に行ったりすると、自分は何もかわってないのに周りの人の反応が全くちがう、何か面白いことをできればガキ大将に従う必要なくなる、といった体験から、自分は一人の人間でも、置かれている文脈で自分の存在って変わるんだな、という理解をしました。
つまり、ものごとにもともと絶対的な意味はなくて、文脈にもとづいて解釈されてはじめて意味が与えられる、いうなれば、文脈と意味は表裏をなすもので、そこでの意味とはある文脈をもとにしたひとつの「解釈」なのだと思いました。
こうした経験から、違う場所に自分を置くことで違う目で自分を見ることは面白いし、ある場所でなんでもないことが別の場所で価値があるということも多々あるよな、と思うようになりました。複数の文脈に身を置き、複数の視点を持ちながら、境界を行きつ戻りつしながらその線上で自分を活かす方法はないかなどと考えました。
一方で、その時自分はバイオリンを弾いていたのですが、なぜか何か新しいものをつくりたいという気持ちを持っていました。
しかし、ほかのスポーツや芸事、学問にも通じることですが、クラシック音楽は才能の有無が極端にものをいう世界で、たとえば天才は5歳で才能の持ち主であるとわかります。そういう意味では凡人がいくら努力しても天才の域には全く近づけない(天才は天才なので当たり前なんですが)、ある意味救いのない世界です。生み出すことの閾値が非常に高い世界だと思います。ここで私は、何か創り出したいと思いつつも、自分の才能のなさに不甲斐なさを感じていました。
自分なりに視野を広げていく中で、徐々にクラシック音楽が表現できない音楽性があることにも気づき、学生時代以降はテクノやハウスなど「4つ打ちの音楽」に傾倒しました。学生時代は平日の夜に渋谷の小さな箱でDJをやったり、友達とイベントを開いたりしつつ、社会人になってからも5年くらいはクラブや野外のイベントを手伝っていました。
テクノやハウスに限らずヒップホップなども含めたクラブ音楽の面白さは、サンプリングとミックスです。自分が大作曲家のように音楽をつくる才能がなくても、誰かが創った素材を組合わせた表現をつくることで自分の音楽を生み出すことができる。
(今はDJが自分の曲を使うことが多いですが当時はわりと)DJは、クラシックの演奏家のように自分の解釈で演奏するということすらしない、ひたすら他の人の曲を引用し組合せるという行為を通じて、そのフロアの雰囲気を汲み取りながら、個々の楽曲の組合せで流れをつくり、即興的にひとつの音楽をつくります。そこで個々の曲は流れに応じてその時々の解釈をされて活かされていきます。ここで私は、文脈は自分が創ってよいという自由さや、その文脈により個々の楽曲がその時々に放つ色や光が変化するのが楽しく、クラブ音楽にのめりこみました。
また人が集まる組織にも似たような考え方を応用できるのではないかと考えたのも同じ時期でした。組織とは、人を組合せることで全体として新しい価値を生み出す仕組みであり、ある目的や文化などのもとで個々人の役割や貢献つまり組織にとっての意味がうまれ、その存在意義を通じてそれぞれのやりがいなどが生まれるのではないかと考えました。このため、大学(*1)の卒業論文では「解釈の多様性が創造性を産む」という組織論のテーマでフィールドワーク研究をしました。
こうした経験を踏まえて、単一の視点や手法ではなく、様々な要素を組み合わせ解釈し直すことで、新しい価値が生み出されると考えるに至りました。(*2)
この考え方は、Zenportの持つ価値が個々のお客様の文脈によっても、他のシステムとの連携によって変化するというソリューションの在り方にも反映されています。
また、グローバルサプライチェーンで、ひとつの取引を異なる視点で捉え、携わる多数の人々のそれぞれの機能や能力を活かす場を創り出したいという、事業コンセプトにも生かされています。
こうした思いが、「互いの違いが、活きる世界へ。」というZenportのビジョンに込められています。
(*1)
一橋大学商学部経営学科楠木建ゼミ。「解釈多様性と存在多様性」というタイトルで、認知と属性の多様性の強さで組織の2類型を想定し、それぞれのリーダーシップスタイル、意思決定プロセスとそこにおけるメンバーのエンゲージメントを研究しました。フィールドワークは、大学のあった国立市の2つのろうあ者支援NPOに参加させていただき実施しました。(*2)
余談になりますが、この考え方は今日のシステム構築にも適用可能だと思います。
SaaSは、サーバやインフラを始めとして誰かがつくった様々なライブラリやサービスを引用し組合せて構築する点で構造が似ています。お客様の役に立つかというプロダクトコンセプトの視点で、既存の技術を選定し、自分たちが構築するサービスに活用されていきます。
またコンパウンドスタートアップも、複数の「Point of Solution」を持ち、お客様の文脈に合わせてそのどれかが起点になり、複合的に価値提供していくという意味で似ています。
そのほか、コンポーザブルERPや、アンバンドルからリバンドルという潮流なども、分散したシステムがユースケースにしたがって意味を変えながら統合されていく点で、同じような考え方を適用できると考えます。
Q.FumiさんがZenportに入社するまでの経緯ときっかけを教えてください。
バリューチェーンの中で様々なプレイヤーの能力をパートナーとして組合せて価値を創造したい、という志望動機で、大学卒業後、三菱商事に入社しました。そこで日本の製造業のお客様とお仕事をしていく中で、韓国や中国に製造業の主導権が渡っていく場面を身をもって感じました。
今でこそ円安や日本の賃金レベル、経済安全保障などの影響で、半導体を始めとして日本国内でも製造業の盛り上がりがあります。しかし、日本が1980年代に米国から製造業の覇権を奪取したのと同様に、2000年代以降、日本でも造船、電機など多くの製造業が主導的地位を失いました。
私が担当していた化学品でも中国資本の最新鋭工場が立ち上がり、安価な類似品を販売するなどしていました。またBCGでも大手製造業へのプロジェクト営業に携わるなどする中で、当時の日本の大手製造業の苦境を経験しました。
しかしこうした製造業など実体のある仕事が人件費の低い地域に移っていくことが必然の流れだとしたら、日本を始めとした人件費の高い先進国はそのように生き残っていくのか、こうした疑問が残りました。
その後、機械部品のファブレスメーカーであるミスミという企業でVOC(顧客の声)という業務の立ち上げを担当し、お客様の声をもとにしたサービス構築の仕組みをゼロから構築する機会をいただきました。合計すると3万件くらいはお客様の声を読んだと記憶しています。そのひとつひとつを解釈して、その中で重要と思うものを選んで社内に発信しつつ、この活動を基に、声を集めるシステム、そこで得られる顧客インサイトをサービス構築に昇華するための会議体、運営チームをつくらせてもらいました。個人褒賞も頂きました。
ここでの発見は、お客様の声を自社のサービスに活用するのは実はDJのようなことだということです。お客様の声を解釈し、組合せて新しい文脈を創りますが、もともと声のひとつひとつは(不具合に対する声を除くと)究極的には正しいとも間違っているともいえません。声自体はお客様の視点、バイアスで述べられており、なかにはそのお声の文字通り新機能を実現すると逆にサービスが使いにくくなってしまうケースもあります。
お客様のペインポイントを、より広く見た標準的なお客様のご利用方法の文脈に載せて、自社が提供したサービス価値の視点で「解釈」することで初めて声を活用する具体的な方法を見出すことができます。
これに気づいた時に自分の中では「何かを創る」ことの最後のピースが埋まった気がしました。これまで商社、ビジネススクール、コンサルを含めて、ビジネスの様々な要素を学んできましたが、どうしても「何か始めよう」と考えるといつも何かが欠けている感じがしていましたが、そのミッシングピースが明らかになったと思いました。サービスの構想は自分の空っぽの内面から出てくるのではなく、DJのように目の前にあるお客様の声を解釈して紡ぐことで創り出せるのです。
そう考えると、いろいろなものが一気につながり始めました。
以前から持っていた、日本を含め成熟した先進国が製造業なしにどのように生き残るのかという疑問については、日本に蓄積されている製造業や国際取引の業務プロセスの知を活用した、ソフトウエアを通じた「知の事業化」がひとつの解になるのではないかと考えました。日本はこれまで製造業や海外との取引で大きな成功を収めてきましたので、そうした点で、日本でこの事業をはじめるのはアドバンテージになるのではないかと思いました。(この試みはGEではうまくいきませんでしたが、Siemensはそのような事業展開をしていると感じます。)
また、前職のミスミの事業モデル(*3)は非常に面白くて好きなのですが、これはシステムでBtoBサービスを構築する考え方にも活かせるのではないかと考えました。「標準化されたカスタマイゼーション」という考え方です。
これは、サービスの中にはじめからカスタマイズを設定できる選択肢や変数を設け、その設定の組合せでカスタマイズを実現するという考え方です。100%のカスタマイズはできないのですが、それでも設定によっては相当レベルの自由度を低コストで実現することが可能です。(CustomizableとCofigurableという対比で表現されることもあります)
企業の業務プロセス、例えば受発注から納品までのプロセスを考えても、企業ごと商品ごとに千差万別です。しかしプロセスごとに名前がついているくらいですから、そこには何らか標準化できる骨格があるはずで、そこにカスタマイズできる意味のある選択肢や変数を用意できれば、カスタマイゼーションを標準化したプラットフォームを実現できるのではないかと考えました。
当時BtoBの業務ソフトウエア領域はブルーオーシャンに思われ、事業を立ち上げたいと考えていた時に、偶然にもヘッドハンティング会社から声をかけて頂きました。そして創業者と「複雑なBtoB業務を民主化する」というビジョンがぴったりと合ったことをきっかけに、Zenportに入社しました。Zenportは当時から国際的なチームで英語で業務をしており、そうした国際性も魅力でした。
当初採用されたポジションはセールスでしたが、当時の事業の状況から、三菱商事やミスミで得たグローバルサプライチェーンや製造業、流通業のドメイン知識があり、BCGで戦略コンサルも少しはやったんでしょ、ということで、自分がプロダクトの戦略もふくめ再構築することになり、プロダクトと営業を担当することからスタートしました。
Q. サービス立ち上げ当時の苦悩を教えてください。
とにかくお客様にヒアリングを重ねました。その中で、多数の関係者間での業務連携の中にペインポイントがあるという仮説が見えてきました。そして展示会に出店して飛び込みで出展者の方と名刺交換するなども含め、数百社の方とお話を重ねながら、仮説を深めて行きました。
サプライチェーンでは、ひとつの取引が、発注・受注・生産・出荷・物流・在庫などのプロセスがそれぞれ異なる会社・部署で管理されています。そこでは、みなさんが同じひとつの取引を見ていますが、実際には、発注は注文単位、出荷は出荷単位、物流は輸送単位など、それぞれ別々の見方をしています。そうした中で、情報はプロセスを通じて次の人へと伝達しますが、受取るたびに、受取った情報の見方を、輸送単位から注文単位へ、など手元で変換していて、手戻りも頻繁にあるので、お互いにいつも情報を読み換えています。そして多くの場合でそこでエクセルが使用されています。
ここで、ひとつの取引は、業務によって人ごとに異なる意味を持っている、つまり取引は色々な視点が交錯するホログラフィのようなものだというインサイトを得ました。
そこには自分の商社での経験も反映されていたと思います。商社で色々な関係者の間に入ってさせていただいたお仕事は、立場の異なる方々をつなぐことであり、そこにはそれぞれの立場の方たちにそれぞれの立場の見方で取引を説明し、合意形成していくことだったと改めて理解しました。
しかしそうしてみると、大変僭越ではありますが、お客様がみなさま「うちのは特別なんだよ」とおっしゃるエクセルを何百回となく拝見していて、だんだんと共通した構造がうっすらと浮かび上がって見えるようになりました。
そこでZenportが提供する価値としては、立場が異なる人たちのそれぞれの文脈に沿って、ひとつの取引を多面的な見せ方をすることで、広義のコミュニケーションコストを減らし、人々と業務をつないでいくことなのだと思うに至りました。
私は、当時メンバーだった英国系フランス人のエンジニアと、ベトナム系ハワイ人のデザイナ・プロダクトマネージャを含めたチームで、複雑で変更の多いプロセスを分析しました。
私がお客様から伺ったサプライチェーンに関る複雑なデータや煩雑なコミュニケーション、ワークフローについて話をして、それをエンジニアがホワイトボードに「いろいろ言っているのは要はこういうことでしょ」という具合に線と丸を描いてデータスキーマの原型をつくってくれました。画面については、かなりチームで試行錯誤しましたが、ゲーム好きだったデザイナが私の話を聞きながら多元的なデータを二次元に落としこむデザインをしてくれました。
しかし実際にお客様にお使いいただく上で立ちはだかったのはデータ連携の難しさでした。
データを手入力で行うのは多くの場合システムへの転記などとの二重作業になってしまい意味がない上に、複数のデータソースからのデータ取込が必要で、その立ち上げには本当に苦労しました。初期の頃は、私自身、BCGで多少なりとも学んだエクセルスキルのすべてを投入しながら、まるまるひと夏お客様のデータクレンジングとデータ連携、そしてデータ連携機能の構築に費やしたこともあります。
少しずつお客様に使って頂き始めた時期にも、プロダクト開発と営業を同時に進める中で、他のメンバーとともに、私自身も、夜中あるいは早朝にエクセルでロジックを作成して、データ投入をおこなう日々が続きました。
また、一般的には「データ連携」では、連携サービス提供者側のデータフォーマットに合わせお客様にデータをご用意いただきます。しかし、本当にお客様に価値あるデータ表示をしようとすると、お客様とどのようにデータを表示するか議論の必要があることに気づき、データ連携方法の構築をZenportが担うことにしました。
ただこのようなことをやっている会社は他にはないため、営業担当者からは「このような手離れの悪いプロダクトではお客様に営業できない」、投資家からは「このようにリードタイムが長く専門知識が必要なサービスはスケールしない」といった厳しい意見をいただき続けました。
私はその度に、Y Combinatorのポール・グレアム氏の「スケールしないことをやれ」という言葉を思い起こし、誰もやっていないけれど、お客様にとって必要なツールこそ、大手企業がやらない、スタートアップが提供する意味のあるプロダクトになると信じて愚直に開発と改善を進めました。そうしているうちにだんだんにお客様にもお役に立てている実感が持てるようになりました。そして今、Zenport は独自の標準データ連携基盤を持つまでに至っています。
そのほか苦労ということでいうと、特許も一度差し戻されました。「複数のソースデータを繋ぎ合わせ見える化し、様々な立場の人たちが同じデータを違う視点で見る」というZenportの核となる機能で特許を申請したのですが、一度は米国にほぼ同じ特許があるという理由で差し戻されました。それは確かに非常に似ていたので、夜中に文字通り目を皿にしてその特許を読込み、機能だけでなく機能の目的、つまりお客様へ提供できる価値の違いをもとに再申請し、なんとか特許取得に至ったようなこともありました。(特許第6739744号 物流管理装置、物流管理方法及び物流管理プログラム)
このように、Zenportは様々な困難に直面してきましたが、そのたびに根本に立ち返り、お客様の視点に立ち続け、愚直に改善を積み重ねると同時に、新しい視点をご提供しようと試みることで発展してきました。
Zenportのミッションである「グローバルサプライチェーンに、共通言語を。」は、まさにこの経緯の通り、異なる立場の人たちの視点をお互いに変換し通訳する基盤を創ろう、そこに立ち現れるホログラフィーをサービスにしようという思いから生まれました。
Q. Zenportは、国籍やバックグラウンドが異なるメンバーが集まっていると思いますが、ダイバシティーの組織をつくっている理由は何ですか?
ダイバーシティが自分にとって大きな意味を持ったきっかけは、三菱商事勤務時に、MBA取得のためにスイス ローザンヌのIMDへ留学した際に得た「Life Changingな体験」が基になっています。
世界40ヵ国以上から来た90名が、グループワークでグローバルな環境でのリーダーシップを学ぶプログラムで、1年のカリキュラムの半分は7、8人ほどでのグループワークが占めます。面白いのは、学校が意図的に話が合わずけんかになようなチームを組み、圧力釜のようなプレッシャーの中に放り込むことです。たとえば国籍はもちろん年齢、ジェンダー、出身業界や職種などがかぶらないチームで、初日の入学式終わった午後4時にビジネスケースを渡され、翌朝9時にチームプレゼンをするといったハードさです。
私の最初のグループはその中でも学年で最もけんかが激しく(笑)、議論の最中にけんかになり、殴り合いこそありませんでしたが、部屋を出て行ったり、机をたたいたり、椅子を投げたりしたこともあります。先日当時のチームメンバーがオランダから東京に来た際にも「あれは本当にひどかった」と笑いあったほどです。(いい思い出です)
しかし面白いことに、こうして毎日のようにやりあっている中で、多様な視点が有機的に組み込まれているときにアウトプットが高まることに気づき始めます。
共通目標、ここではあたえられたビジネスケースで最良の戦略を練り、判断を行うということですが、この目標に向かって自分が出せるものを出しつくし、それをチームが受け止め、その目標に資するように解釈して統合し、戦略などの文脈や視点を更新していくと、非常に厚みのあるアウトプットになっていきます。
チームは、あらゆる点で共通点がないメンバーで構成されています。ひとつの事業を論じるにも、エンジニア、法務、財務、営業、国際展開といった多様な視点で見ることができ、更にそこに地域による違いも加味されます。そうした多様な視点で自分たちのアウトプットを批判的に、かつ創造的にたたき上げていくと、盲点がなくなっていきます。あたかも身体中の筋肉を効果的に鍛え、どこから殴られても蹴られても崩れないからだをつくっていくような感じです。
また私は、学校代表チームにくじ引きで選ばれ(話し合いではもめてしまい絶対に代表を選べないことだけはクラス全員がわかっていため、くじ引きだけはすんなりと決まった記憶があります(笑))、欧州ビジネススクールのビジネスケースコンテクストに出たのですが、他のメンバーが超優秀だったこともありチームは優勝しました。その時に感じたのは、「いわゆるリーダー」がいるチームは、リーダーの盲点がチームの弱点になってしまう、したがい、色々な視点が統合されているわれわれのような方法はチームとして創造性を最大化することができていそう、ということです。
しかしこの留学で本当にLife Changingだったのは、最後は表面上の違いを超えて人間関係が「透明」になる経験です。自分を含め誰しもが人としての弱点や条件反射してしまうクセを持っていますが、本気で目標を共にすることができると、そうしたクセを超えて本当に理解し合い、お互いを活かしあうことができる。これは自分の持つ能力をチームの文脈の中で新に解釈してお互いに使う、ということです。これを体験できたことは非常に幸せなことだと思います。
ただそこに至るには、自分の嫌なところも、グループダイナミクスのいやらしさにも自覚的にならないといけません。よく「部屋の中にいるゾウ」といわれたりしますが、IMDでは「Fish on the table」という言葉がしきりとつかわれていました。自分が無意識にでも絡めとられてしまうエゴ、つまり私心や欲、自尊心、反応といったものや、自分をまもったり有利にするための暗黙の集団的な行動、思考といったことを知覚することで、自分たちをもっと目的にむかってよりよく進める集団に変えていくことができるという体験です。
さまざまな視点を持つ多様性のあるチームが、ひとつの方向に向かってまとまると、ひとりひとりは天才でなくとも、チームとしては非常に創造的で革新的になることができます。
私が考える多様性とは、単に国籍や人種、性別やバックグラウンドが異なる人でなく、異質や違いを受け容れ、それを新しいものに昇華できることです。共通のゴールを持ち、同じ方向へ向かっていく。その過程で意見や方法は違っていても構いません。
Zenportでは「Agree to disagree」を尊重しています(*4)。違うこと自体は何かまずいわけではありません。違うことはむしろ機会です。違いを認めることが第一歩で、そこに共に成し遂げる目標と意志があれば、その違いから化学反応を起こし、エゴに絡めとられずに革新的な解法を導く正しい意思決定をしていくことができます。
その「違い」は違和感を通じて自覚されます。したがい、大事なのは、そうした違和感を理解しようとする姿勢や、その違いに対して面白みを感じて、受け入れて、より良いものを共創していくことだと考えています。
特に弊社のようなスタートアップ企業では、ロードマップは変化していきますし、リソースも十分でないため、場合によっては業務内容も更新されていきます。変化に対して前向きに捉えて、そのなかで自分の役割ややるべきことを見出せる人、自分を異なる視点から理解し、前向きに表現できる「視点の多様性を持つ人」がZenportでは活躍しています。
これは簡単なことではありませんが、私自身は、IMDと同様、Zenportが、多様性のあるチームとして一丸で目的を追求し、新しい価値をグローバルな市場で創り出していくことで、Life Changingな経験をし、Life Experienceを共有できる場にし続けることが私の役割だと考えています。
(*4)
これはメンバーの一人の指摘から始まりました。
Q. 多様性を持つ人の共通点や特徴はありますか?
よく、インターナショナルなバックグラウンドを持つ人が「多様性をわかる人」と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。Zenportで「多様性」とは「認知の多様性とそれを活かすマインドセット」を意味します。
私が考える認知多様性を持つ人の共通点として、逆境のなかでも挑戦してきた経験があることです。時には否定されながらも、自分の弱さや痛みを理解して謙虚に振る舞える人は、他の人の目からどう見えるのか考える多様なものの見方を理解しています。
したがい、チームの中では、認知多様性を持つ人は自分の弱さ(Vulnerability)を認め、それを公表してチームの中で活かす強さを発揮します。
それがない人は、人の意見や異なる考え方を受け入れることが難しいことが多いと感じます。また、健全な批判を自分に対する否定と捉えてしまう傾向があるようにも感じます。
私は偉そうにここで色々と語っていますが、しかし私も含め完璧な人はいません。自分自身を振り返っても、エゴ、つまり私心や自分の欲、自尊心、何かへの反応に気づき、それを超えるというのは、たとえばスタートアップのようなハイプレッシャーの中などでは時に非常に難しいです。
しかし、他者の視点を想像し、自分を相対化しメタ認知することは、われわれのように多数の立場の方たちを国や企業をまたいでつないでいて、かつ大企業向けに提供しているサービスでは最も重要な視点の一つです。
これは、サービス開発やお客様のオンボーディングでの議論では当然のこと、障害対応なども含めて信頼いただけるサービスとしてZenportを発展させる上で常に意識しなくてはなりません。お客様、あるいはステークホルダーの皆さんの目線で自分たちの活動やサービスをご説明できるように準備することは、説明責任(Accountability )として、日々研鑽が必要な点だと考えています。
他方この文脈でいえば、私自身の言動が正しいとは限らない、ということも当然あります。したがい、特に幹部社員には、私の考え方を相対化し、私に意見し何が正しいのか議論することが最も重要な役割のひとつであることを伝えています。逆にお互い建設的な批判を行い、それを受け容れ、それに基づく建設的な議論ができる人がZenportでは評価され昇進します。
Zenportには、1つのコアバリューと5つのバリューがありますが、その根底にあるのは、ここで述べた「エゴ、つまり私心や自分の欲、自尊心などを横において、ひとりでは達成できない大きなものをチームで共に成長しながら創っていく」という価値観です。
コアバリュー:多様性から革新をつむぐ(Leverage diversity to drive innovation)
バリュー
1. 透明性 / 私心や個人の欲を超えた、価値観に基づく一貫した行動 / 説明責任
(Transparency / Integrity / Accountability)2. お客様とチームへのコミットメント(Commitment to client and team)
3. 勇気を持った決断(Fearlessness)
4. 目標に向けたエゴのない対等な協力(Collaboration)
5. お客様とチームのための先読みと自発性(Proactivity)
実は私は、これはZenportで指向する価値観であるばかりではなく、世界に今必要な素養だと考えています。
第二次世界大戦後、冷戦の終結を経て、長らくパックス・アメリカーナとも呼ばれる時代が続いてきました。しかしそうした世界が目下急激に変化しています。「分断」と表現されることが多いですが、私は「多元化」という、これまで支配的だった西欧的な価値観が相対化された世界が出現していると思います。
そうした多元化した世界で、Zenportは「データ、人々、経済をつなぎ、持続可能で協力的な世界を。」というパーパスを持ち、グローバルサプライチェーンを通じて世界をつないでゆきたいと考えています。ぜひこうしたパーパスに共感頂ける方に参画いただきたいです。
Q. Zenportの今後の展望について教えてください。
Zenportは、分断しない世界をつくっていきたい、世界の人々が協業して持続可能な姿で豊かになっていく世界を創りたいと考えています。この思いは先ほど述べました、ビジョン、ミッション、パーパスに凝縮されています。(*4)
その中でZenportはお客様への提供機能の中心に「データ連携」を据えています。私はグローバルサプライチェーンにおける安価で柔軟なデータ連携は「20年後のあたり前」になる(*5)と思っています。実際に今すでに、日本で誰もが名前を知る産業界のリーダー企業様がZenportをご採用いただき始めていますし、後に述べるように、世界を代表する企業が俊敏な戦略実行をする上で必須の能力になっていくと考えているためです。
Zenportは例えるなら、グローバルサプライチェーンのデータ連携におけるSpaceXです。
Zenportは、これまで高価で時間のかかるグローバルサプライチェーンのデータ連携を圧倒的な安価、短期間でご用意し、プロセス、地域などを超えて一元的に可視化します。これによりデータ、人、ビジネスを結び連携した世界の構築に貢献します。
みなさんご存知のイーロンマスクの宇宙事業であるSpaceXは、燃料がロケットの機体と比較するとはるかに安価であることに着目し、燃料をふんだんに使うことで機体を再利用可能にしました。(機体がもっとも損耗するタイミングは着陸時で、空気が機体と摩擦を起こして燃えてしまうためだそうです)
これにより、打ち上げコストを20分の1に減らし、結果、年間100回近くの驚異的な回数の打ち上げを実現しています。同社にけん引される形で、世界のロケット打ち上げ回数も2019年から2023年の4年間で2倍以上の200回以上に成長しました。圧倒的なコスト削減が市場を変革し、新しい市場を形成しているとすらいえます。
Zenportは、データ連携のロジックを抽象化し、標準的なデータ構造として再利用可能な形にすることで、圧倒的なコストメリットでデータ連携を可能にします。これにより、お客様は市場の変化や戦略の変更に応じて、データ連携を進化し続けることが可能になります。
コロナ以降、環境の変化を実感する出来事が続いています。毎年耳にする「過去最大級の台風」、「最高気温更新」といった気候変動、世界各地で噴出するさまざまな感情や紛争など。そうした目に見えるもの、体感されるものから、人口動態や富の移動といった静かにしかし確実に変化している地殻変動、技術的にはAIの能力の飛躍的な向上などもあります。これまでの前提が深いレベルで変化しているといえます。
一方で、世界の経済はこれまで以上に複雑かつ強固に結びついています。もちろん経済安全保障の観点からサプライチェーンの分断を言われていますし、各国間での資源獲得競争はますます厳しさを増していくと思います。しかし冷戦時の東西陣営のように完全にサプライチェーンを分断することは不可能であり、世界はまるで無数の糸がからまりあったひとつの大きな玉として絶えず変化しながら転がっていくように見えます。
そうした中、大企業もこの厳しい変化の下で事業を進化を志向されています。気候変動を受けたクリーンエネルギーの活用や、国内市場の収縮にともなう海外取引の強化、またこれまで培ったグローバルな事業をより海外拠点を軸にした展開など。さらに同時にコスト削減への強い意志があったりします。
コロナを経て、需要・供給・輸送の状況が一変しており、今後も想定を超える事態が起きる可能性がある、という強い危機感をお持ちなのだと思います。エクセレントカンパニーと呼ばれる企業であればあるほど、売上高が如何に大きくとも、事業領域、オペレーション、収益すべての面で変革するという妥協なく強い意志を感じます。
変革にはスピードが求められます。しかし従来のシステム連携の方法では、変革に対応するデータ整備だけに、数年と10億円単位での投資が必要になります。この内容は、たとえばグループ企業間取引のデータをより精緻にリアルタイムに見える化することであったり、リアルタイムに更新されていくデータをプロセス間で結び付けるといったことです。
こうした背景からZenportのような柔軟で俊敏性の高いサービスが求められています。このようなトレンドからは、Gartnerがコロナ前の2020年に提唱した「コンポーザブルERP」という概念が実際に実現されていく過程を目の当たりにしているかのようです。
このようにZenportは、データ連携の革新を通じて、多元化していく変化の激しい時代に求められる俊敏性と持続可能性を実現し、人々と企業が協調して豊かになれる世界の実現を目指しています。
(*5)
ビジョン:互いの違いが、活きる世界へ。
ミッション:グローバルサプライチェーンに、共通言語を。
パーパス:データ、人々、経済をつなぎ、持続可能で協力的な世界を。(*6)
LayerX福島良典CEO、東京大学FoundX馬田隆明ディレクターそれぞれのお話に共感してこのように表現しています。
https://www.fastgrow.jp/articles/layerx-fukushima-02
https://blog.takaumada.com/entry/make-something
Q.最後にこれからJoinしてくるメンバーへメッセージをお願いします。
先ほど述べたように世界は多元化していきます。したがい、今ほどそれぞれの人が培ってきた異なる知や視座を組合せることが必要な時代はありません。
さきほども述べましたが、Zenportは「Agree to Disagree」を出発点に議論を突き詰め、エゴや私心を超えて、お客様や事業を第一に置いて意思決定をしていくチームです。
「互いの違いが、活きる世界へ。」というビジョンのもと、それぞれの違いを活かして「データ、人々、経済をつなぎ、持続可能で協力的な世界」を一緒に構築していきます。
人生は決して長いものではありません。その人生の中で、こうした多様性のある組織で、志を共にして働き、世界を舞台に市場を創り出していくことができれば、これはLife Changingであるだけでなく、Life Experienceそのものです。私自身は、ここで働くひとにとっては、Zenportをそういう場にしていきたいと常に考えています。
ただ、そうした働き方は必ずしも簡単ではありません。したがい、自分の弱さや違和感、自尊心などのエゴと向き合える方、自身を他者の視点から相対視して新しい視座を生み出せる方や、スタートアップという不完全かつ制約のある環境を、創造性を発揮できる機会と捉えられる方にぜひ、弊社で挑戦していただきたいと考えています。
エンジニアの皆さんにとっても、ビジネスサイドの皆さんにとっても、Zenportは社内外のリソース、そしてPoint of Solutionを組合せて複利的に(コンパウンドに)価値を創造していく場です。もしこうした価値創造にご興味がありましたらぜひご連絡ください。カジュアルにでもぜひ議論させてください。
多様な考え方を化学反応させ、データ・人・経済をつなぎ、イノベーション、未来を一緒に創っていきましょう!
Fumiさんありがとうございました。
今後さらなるZenportの成長が楽しみです!
\私たちと一緒に成長したい方はこちら/
We, Zenport, are committed to “Connecting data, people, and economies to create a sustainable and cooperative world.” We want to create a world that is not divided, a world where people around the world collaborate and prosper in a sustainable manner through global supply chains, using data collaboration as a starting point.
This is the third in a series of articles introducing our diverse members and their working styles. We interview Eliot, our VP of Engineering, who has a unique background as a chemistry teacher turned engineer.
Contents:
- Introduce himself and reason for Joining Zenport
- Growth and Technology in the Supply Chain Industry
- On building a team around Zenport’s diversity
- For engineers who are challenging new areas

Introduce himself and reason for Joining Zenport
In the realm of software engineering, the paths taken by professionals often wind through computer science programs and technical internships. However, there are those whose journeys defy convention, weaving through unexpected territories before finding their calling in code. Eliot, currently serving as the Vice President of Software Engineering at Zenport, is one such individual.
Interviewer:Could you walk us through how you transitioned from studying chemistry to pursuing a career in technology?
Eliot:Certainly. After completing my Master’s degree in chemistry in the UK, I embarked on a Ph.D. program in the same field. However, I eventually decided to chart a different course. Japan beckoned, offering a fresh start. I found myself teaching chemistry at a private tutoring institution in Tokyo, catering to a diverse group of students, including those from international schools.
Interviewer:That is a very unique career. How did you come to join Zenport?
Eliot:My path eventually led me to Zenport, where I initially joined as a front-end engineer based in Tokyo. Over the years, I’ve had the opportunity to evolve within the company, taking on new challenges and responsibilities. Today, as the Vice President of Software Engineering, my role encompasses not only front-end development but also full-stack support for the business. Zenport has provided an environment conducive to growth and innovation, making it an exceptional place to nurture one’s career.
Interviewer:What drew you to the intersection of technology and supply chain management, particularly at Zenport?
Eliot:Initially, it was the allure of the supply chain domain that piqued my interest. Joining Zenport during a time when the world was grappling with the repercussions of the COVID-19 pandemic provided me with a unique perspective. Witnessing the disruptions and challenges faced by global supply chains highlighted the critical role of technology in mitigating such crises. Whether it was navigating lockdowns in mainland China or the fallout from the Suez Canal blockage, these events underscored the fragility of supply chain management and the need for innovative solutions.
Growth and Technology in the Supply Chain Industry
Interviewer:Zenport’s goal of becoming the common language for supply chain management. Could you elaborate on how Zenport is navigating the integration of modern technology with legacy systems?
Eliot:Many of the companies we collaborate with, particularly in Japan, have entrenched systems dating back several decades. Each of these companies has developed a unique approach to resource planning and operations, often relying on tools like Microsoft Excel and proprietary software. At Zenport, our aim is to unify these disparate systems into a centralised platform, serving as a hub for supply chain management. We envision Zenport as the common language that bridges the gap between these legacy systems and modern solutions.
Interviewer:I see. Next, let’s move on to the topic of “diversity,” which Zenport places great importance on.
Eliot:When we say diversity, what we really mean is diversity of thought. We believe that true innovation stems from differing perspectives and ideas. This diversity in thinking is what drives our approach to problem-solving and our culture of innovation.
Interviewer:How does Zenport cultivate an environment that encourages diverse thinking among its team members?
Eliot:At Zenport, we embrace the notion that diversity in thought leads to robust solutions and improved outcomes. We actively seek out team members with varying backgrounds, experiences, and perspectives, recognizing the value they bring to the table.
In a field where innovation is paramount, having team members with diverse backgrounds and ways of thinking is invaluable. Whether it’s tackling complex technical challenges or devising strategies for product development, the diversity of thought within our team allows us to approach problems from multiple angles and uncover innovative solutions that may not have been apparent otherwise.
Interviewer:Zenport has members from ● countries around the world. Could you provide some insights into the structure of Zenport’s engineering team and how it operates across different locations?
Eliot:Certainly. At Zenport, we strive to maintain an environment of equality and collaboration within our engineering team. Rather than categorising team members into hierarchies based on seniority, we promote a culture where everyone’s opinion is valued equally. This fosters a sense of ownership and empowers individuals to contribute their ideas and expertise to problem-solving efforts.
Our engineering team comprises individuals from various locations, including Japan, Canada, India, and Hong Kong. While most team members are based in Japan, we make accommodations to facilitate collaboration across different time zones. We recognize that remote work requires a high level of trust between team members and foster an environment where individuals have the autonomy to manage their own work schedules and styles. We value trust above all else in working remotely, in different locations.
For engineers who are challenging new areas
Interviewer:By the way, how do you keep yourself up to date with those new technologies and skills? I think engineers need to keep up with new technologies.
Eliot:Well, it’s a constant endeavor.Whether it’s cutting-edge technologies or areas where my knowledge could use a boost, I make a conscious effort to stay informed and continuously enhance my skill set.
One of my go-to resources is tech podcasts. I find them to be an incredibly convenient and effective way to stay updated on the latest developments. There are several active podcasters in the tech community who consistently deliver insightful discussions and analyses on a wide range of topics.
Just a few days ago, I came across a podcast discussing a significant security issue in open-source software. It was a topic that immediately caught my interest. From there, I delved deeper into the topic by conducting additional research online.
Interviewer:Many engineers are currently interested in Zenport.The candidates from other industries, they probably might find it difficult to change to the supply chain logistics industry. Do you have any advice to catch up ?
Eliot:Industry experience aside, we value mindset above all else.
Supply chain management is far from a stagnant industry. In fact, it’s incredibly dynamic and ripe with opportunities for innovation.
From navigating supply chain disruptions to optimising logistics operations, the challenges faced by the industry are ever-evolving. This creates a fertile ground for new ideas and technologies to emerge, driving innovation and transformation within the sector.Indeed, AI has emerged as a prominent trend in the tech industry, with its applications spanning across various domains. In the context of supply chain management, AI holds tremendous potential to revolutionise operations and drive efficiencies.
At Zenport, we’re actively exploring ways to integrate AI into our software solutions, harnessing its capabilities to empower our clients with actionable insights and greater operational efficiency. By embracing AI, we’re not only staying ahead of the curve but also driving meaningful innovation in the field of supply chain management.
Industry experience is irrelevant, especially if you are willing to boldly take on the challenges of such a promising field.
Interviewer:Finally, do you have a message for future Zenport members?.
Eliot:If you’re seeking a vibrant and dynamic workplace where creativity and curiosity are celebrated, then Zenport is the perfect destination for you. We’re on the lookout for inquisitive and innovative minds who aren’t afraid to challenge the norm and push the boundaries of what’s possible.

Thank you very much Eliot.
\If you are interested in growing with us, please contact us here/